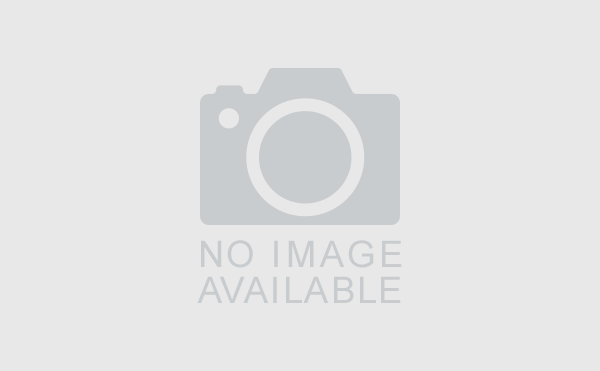仮払い仮処分(民事保全)と保全の必要性
2025年7月27日
事故に伴う損害賠償に関してなされた民事保全法上の仮払い仮処分の債務者側(企業側)で、今般、全面勝訴となり確定しました。仮払い仮処分は、主に不当解雇等を理由とした労働事件で当面の給与を確保するために提起されることが多いのですが、交通事故や労災事故等については近時の裁判例は掲載されていないことから、これらの事故の保全の必要性について具体的に考察・検討できるよう事案の1つとして裁判所の決定(確定)を紹介させていただきます。
1 事案の概要
本件訴訟は、企業側の工場で起きた事故が原因で、企業と契約関係にない債権者(2社の代表取締役)が重傷を負ったため、債権者と同人が代表取締役を務める企業2社が債権者となって、本訴前の民事保全として、企業側に、主位的に2社が被った損害、予備的に債権者個人の休業損害及び治療費等の支出による損害賠償請求権を被担保債権として、申立てから1年先まで毎月一定額の支払いを求めて仮払い仮処分を申し立てた事案です。
企業側は刑事責任としての過失は認められない可能性が高いものの、民事上の過失は認めるとした上で、治療費は認める一方で、差額ベッド代などは被担保債権として認められないこと、及び、保全の必要性の疎明がないと主張していました。
論点はいくつかあったのですが、主な争点は、①債権者が代表取締役をしていた1社の外注費の支出、代表取締役報酬の支出が損害と認められてるか、②もう1社が稼働できなくなったことによる毎月の売上相当額の損害が認められるか、③差額ベッド代、症状固定前の家屋改造費、再生治療の支出予定額が損害と認められるか、及び、④保全の必要性が認められるが主に問題となりました。
2 裁判所の判断
債権者側の準備の都合により審理は異例の約6ヶ月にも及び決定は約7ヶ月後に出されました。裁判所は、一律保全の必要性が認められないとして、債務者側で認めていた一部の治療費なども含め、「債権者らの被保全権利の存否を判断するまでもな」いとして債権者らの請求を全て却下しました。
決定では裁判所は、「民事保全法23条2項に基づく仮の地位を定める仮処分が認められるためには、債権者において、保全の必要性、すなわち、権利関係が確定していないために生ずる「債権者の著しい損害又は急迫な危険」といえる状況があることを疎明しなければならない」とした上で、各債権者の保全の必要性について次のように判断しました。
- 債権者個人
「将来実施を予定しているとされる、 再生医療等製品を用いた治療(疎甲1 5。費用は約465万円)や自宅改装工事(疎甲1 4、 27。費用は395万1686円)については、 通院治療継続中で症状固定していない現時点において、 それらの支出が必要かつ相当なものか、いつ実施するのかが明らかでない。」、「付言すると、 債務者は、 債権者個人に対して損害賠償するに十分な資力を有していることが窺われるのであり(疎乙2、 3参照)、 本案訴訟が終結するまでに支払が困難となるおそれがあるとまでは疎明できない。」「オ 以上によれば、 債権者個人が近い将来生活費や治療費の支払に窮するような経済的困窮状態に陥るとまでは疎明されておらず、本案訴訟の提起までには時聞がかかる見込みであることを考慮しても、本案訴訟の帰結を待たずに仮払いが認められなければ著しい損害又は急迫な危険が生じるとの疎明には足りないので、あって、予備的申立ても含めて保全の必要性の疎明に足りないというべきである。」 - 債権者会社1
「債権者個人の本件事故に起因する傷害により債権者会社1の業務に支障が生じているとしても、それをもって直ちに同社の経営が維持できない状態に陥っているとまでは疎明するに足りない」とし、債権者会社1の主張を前提としても「同表によっても2割強の粗利が生じることからすれば、 債権者会社1の事業継続が殊更厳しくなっていることの裏付けには足りない」とした上で、むしろ、「決算報告書(疎甲1 7)によれば、同日時点で十分な流動資産があり、 健全な財務状況にあることが一応認められるのであり、 本件事故後短期間のうちに債権者会社1の経営が危機に瀕する状況に陥っているとはにわかに考え難い」として、「本案訴訟の帰結を待たずに本件保全申立てにより損害賠償金の仮払いを受けなければ著しい損害又は急迫な危険が生じるとの疎明には足りないのであり、 保全の必要性の疎明に足りない。」と判断しました。 - 債権者会社2
「債権者会社2においては、 本件事故後債権者個人が工事を行えなくなったことにより、 令和6年10月155日を最後に売上の入金が途絶しており、 債権者会社2の○○銀行□□支店における普通預金口座の預金残高が本件事故を境に減少し続けているし(疎甲1 3、 28)、令和7年1月以降債権者個人に対して役員報酬I(従前は月額40万円)の支給をしない状態が続いていることが一応認められるところである。」としつつも、「しかし、債権者会社2は現時点で既に廃業しており(争いがなし)、事業継続のため資金を必要としているなどの事情もない。」、「債権者会社2は、 既に廃業し、 他の業者に事業の引継ぎをした状況にあることからすれば、速やかに本件保全手続による仮払いを受けることが必要な状態にあるとはいえない」として、「以上のとおり、債権者会社2は、 直ちに債務者から損害賠償金の仮払いを得なければ事業を継続できないなどといった状況にはなく、本案訴訟を通じて権利行使をすれば足りるといえるので、あって、 本案訴訟の帰結を待つことなく本件保全手続によらなければ著しい損害又は急迫の危険があるとの疎明には足りず、 保全の必要性を疎明するに足りない。」と判断しました。
これらの決定については、債権者から即時抗告(告知を受けた日から2週間)されることもなく確定し、企業側全面勝訴となりました。
3 違法な民事保全と損害賠償
仮払い仮処分などの民事保全については、通常の訴訟と異なり、申立てが認められなかった場合には、損害賠償義務を負う可能性がある点については十分留意が必要です。この点を見落とした安易な申立ても多いためです。
次の昭和43年最判は、被保全債権が存在しない場合でしたが、保全の必要性が否定された場合でも平成29年大阪高裁で不法行為が認定されており最高裁でも維持されています。
- 最高裁昭和43年12月24日判決・民集22巻13号3428頁
「仮処分命令がその被保全権利が存在しないために当初から不当であるとして異議もしくは上訴手続において取り消され、あるいは本案訴訟において原告敗訴の判決が言い渡され、その判決が確定した場合には、他に特段の事情のない限り、申立人において過失があったものと推認するのが相当である。 - 原田保考「違法な保全処分による損害賠償責任(判例タイムズ710号28頁)
上記昭和43年最判以降1989年までの裁判例については当時の大阪地裁判事が詳細な分析をしています。 - 大阪高等裁判所平成29年4月21日判決・金融・商事判例1570号14頁
「仮処分命令がその被保全権利が存在しないために当初から不当であるとして異議もしくは上訴手続において取り消され、あるいは本案訴訟において原告敗訴の判決が言い渡され、その判決が確定した場合には、他に特段の事情のない限り、申立人において過失があったものと推認するのが相当である(最高裁昭和43年12月24日判決・民集22巻13号3428頁参照)ところ、民事保全法においても、保全すべき権利又は権利関係と保全の必要性はいずれも保全命令の実体的要件であり、いずれかが欠けていれば保全命令は違法であって、保全すべき権利又は権利関係の不存在と保全の必要性の不存在に差異はないというべきであるから、仮差押命令が事後の不服申立手続において保全の必要性の不存在によって取り消された場合にも、他に特段の事情のない限り、申立人において過失があったものと推認するのが相当である。」
「本件仮差押命令は事後の不服申立手続において保全の必要性の不存在によって取り消 されているから、第1審原告には過失があったものと推認することができる。」
「 イ 弁護士費用 138万円 第1審原告の本件仮差押命令申立てによって第1審被告が要した弁護士費用としては138万円が相当である。」
なお、当該大阪高裁判決は、上記とは別に認定された逸失利益については、最高裁判所第1小法廷平成31年3月7日判決・最高裁判所裁判集民事261号87頁で否定され差し戻しとなっていますが、弁護士費用に関する判断は維持されています。
4 コメント
民事保全手続の中でも、仮払い仮処分手続は仮差押等とは異なり保全の必要性の要件が厳格になっています。そのため、当該申立て(中でも保全の必要性)が当該手続又は後の本訴で認められなかった場合や後に本訴で否定された場合には、相応のリスクを負うことになります。
交通事故等において、仮払い仮処分の申立ての実益を説くホームページが存在し、その戦略と一定の実益があることはそのとおりであり、特に、仮払い仮処分は、保険会社等の相手方との交渉や和解の手段として戦略的に採用する弁護士も少なくないようですが、戦略に反して反して争われた場合の帰結についても十分把握しておくことが非常に重要です。
仮払い仮処分以外に、一時的に支払を受ける手段としては、企業側が締結している損害賠償保険の保険会社に対して保険法に基づく先取特権を行使する方法、一部を将来請求とする本訴を提起する方法などが考えられます。
また、企業側としては、一部でも請求が認められるということは、それまでの企業の対応が少なくとも不適切であったことで債権者の生活を困窮させたことになるため、レピュテーションリスクも損するところですので、裁判所の判断をもらう場合には企業とも翌協議の上、慎重に決定する必要があります。
本件では、仮払い仮処分の通常案件と同様、和解の打診がありましたが、債権者側からコンプライアンス上受け入れがたい案が示され修正に応じてくれなかったこと、保全の必要性の要件を満たさないことが明らかであったため、企業とよく協議の上、裁判所の判断を得ることにしたものです。
(文責:弁護士・海事補佐人・海事代理士吉田伸哉)